
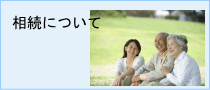

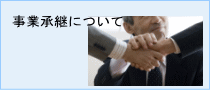
相続税は一つの申告について10人が作成すれば10人とも違う税額が算出される申告書が作成されると言われています。
税理士が税金の計算をすれば誰でも結果は同じというわけではありません。
遺産分割の際に、今回の相続税についての節税を重視する場合と、次の相続を考えての節税を考えて行う場合では税額が違ってきます。
まずは、ご自身の現状を把握していただきたいと思います。相続税が課税される可能性があるのかどうか。
課税されないのでしたら相続税対策を考える必要はないでしょう。
初回相談は無料です!! お気軽にお電話下さい。
遺産が基礎控除以下の場合は、相続税の申告は不要となります。
「基礎控除」とは・・・・3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
夫から見れば妻。 妻から見れば夫。
ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。
民法では子供、養子が何人いても法定相続人とみなします。
ただし、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がありません。
直系卑属が誰もいない時に相続人になることができます。
被相続人の直系卑属や直系尊属が誰もいないときに相続人となることができます。
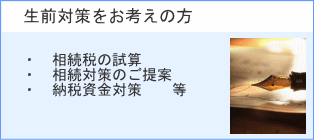
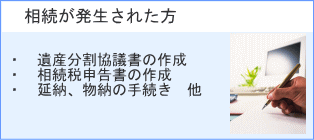
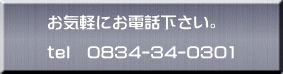
贈与は民法で「当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思表示をして、相手方が受諾することに よって、その効力を生ずる契約である」と定めています。つまり、口約束でもお互いに意思表示をすれば成立する ことになります。
贈与を行うことで、スムーズな『事業承継』や、『相続税の節税』を行うことができます。
贈与税の申告と納税は、1年間に基礎控除額110万円を超える価格の贈与してもらった人が貰った年の翌年2月 1日から3月15日までに贈与してもらった人の所轄の税務署へ申告をしなければいけません。
納税も申告期限も3月15日です。申告期限までに申告しなかった場合は延滞税が発生します。
住宅資金等の贈与を受けた場合、非課税枠を上乗せすることが可能です。
ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与があった場合で、一生に一回利用することができ
ます。
また、この贈与で受けた財産は、贈与者が死亡したときに、みなし相続財産とはなりません。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例があります。
ただし、贈与を受けた年の1月1日における年齢や、年間合計所得金額の制限があります。
相続税の試算をした結果、基礎控除額以内の方にお勧めなのがこの制度です。
この贈与で受けた財産は、贈与者が死亡したときに、遺産に加えて相続税を計算しなければいけません。
従って、相続税がかかる人にはメリットがありません。
しかし、相続税がかからない人ならメリットがあります。
デメリットとすれば・・・
・ 移転コストがかかります。例えば、不動産の贈与を受けると登録免許税や不動産取得税がかかります。
・ 将来、相続税の税制改正があり、これまで相続税がかからなかった人にも相続税がかかる可能性がある。
以上の点を踏まえて、相続時精算課税の適用を受けるのか検討する必要があります。
年間一人当たり110万円まで贈与税がかからないことになっています。
この110万円は贈与を受けた人一人当たりということなので、子供や孫が5人いれば、無税で550万円を移すこ
とができます。たとえば、同じ金額の贈与を5年間続けたとすると2,750万円移すことができます。
ただし、最初の年に2,750万円の贈与があったものとみなされて贈与税がかかってくることもあります。
これを避けるために契約書を作るといった対策が必要となります。
贈与を行って3年以内に相続があった場合は相続財産の対象となってしまいますが、相続権のない孫や嫁に対
して贈与すれば、相続財産に加算されることはありません。
所得税の負担が重いと悩んでいる不動産オーナーは子供に不動産を贈与することで所得税が大幅に
減少します。
所得税は累進税率となっている為、その効果が意外に大きなものになる場合があります。
ただし、手続きが複雑である為、専門家に任せて税金の試算等を行ったうえで検討する必要があります。
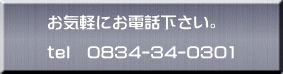
現在、社長の平均引退年齢は60歳代後半といわれています。
今後10年間に事業承継が急増することになると予想されいています。これを受けて税法も円滑に事業承継ができるように改正がされてくると思われます。
今後の改正の動向を踏まえながら現在できる最善の方法を模索することが必要になってきます。
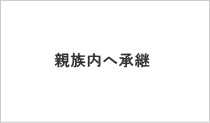
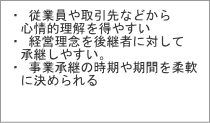
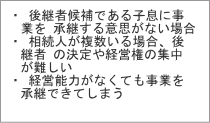
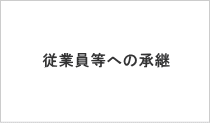
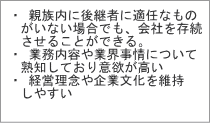
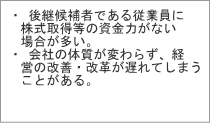
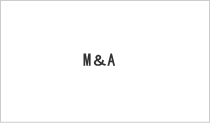
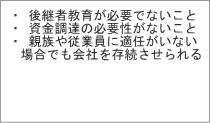
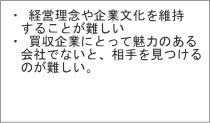
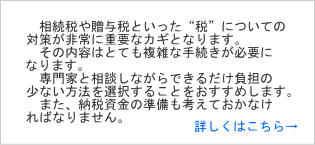
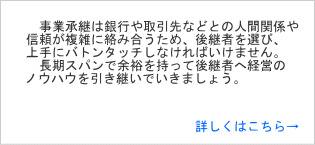
池中信雄税理士事務所
〒745-0017
山口県周南市新町1丁目11
リバティ新町101
TEL 0834-34-0301
FAX 0834-34-0302